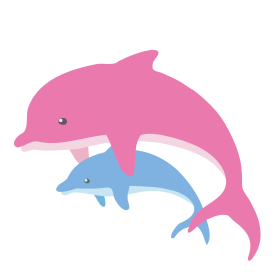- HOME
- 検査機器のご案内
検査機器のご案内
心電図
Cardiofax C (ECG-3150)
信頼の日本光電製心電図です。コンパクトながら綺麗で安定した心電図を測定し、不整脈や虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞など)や心臓の肥大などを検出することができます。
動悸や胸痛、階段で胸が苦しい感じがするといった症状の方に有用な検査です。
レントゲン
富士FPD CALNEOシステム+胸部X線画像病変検出ソフトウエアCXR-AID
AIも活用、精度の高い画像をより低被ばくで実現
富士フィルム製の一般撮影間接変換FPD装置を装備。高画質化と低線量化を実現し、小さなお子様のレントゲンが必要な時でも、より低被ばく量で高画質の画像をとることができます。
また撮影後に現像するためにパネルを毎回外す必要がなく、撮影時間を大幅に短縮できます。
撮影した画像はAI装置による読影がなされ、撮影した医師とダブルチェックを実現することが可能で、レントゲンに映った有意な所見の見落としを大幅に減らすことができます。
レントゲンで所見があったときには武蔵野市立保健センター(東京都武蔵野市吉祥寺北町4丁目8番10号)やメディカルスキャニング武蔵小金井、高円寺にCT精査の紹介状を作成することができます。
尿検査
CLINITEK Status+
尿検査により膀胱炎などの尿路感染の診断、尿潜血、尿糖、尿たんぱくの評価を5分で行うことができます。機械で判定するのでテステープの色の判定も客観的です。
電子カルテとID連携しており、結果が出たら速やかに電子カルテに反映されるので検体取り違いのリスクを最小限に減らすことができます。
全自動血球計数・
免疫反応測定装置査
MEK-1303 セルタックα+
お子様にもやさしい、わずかな採血で検査結果は5分
採血が苦手なお子様でも10μlというわずかな血液があれば測定することができ、5分以内に結果を出すことができます。測定できる項目は以下の通りです。
・白血球(WBC: White Blood Cell)
細菌やウイルスと戦っているときに増えてくる血液の仲間です。体に炎症が起こると上がってくるという意味では後述のCRP(C-reactive protein)と同じかもしれませんが、CRPよりも早く上がってくる傾向にあるのと、細菌感染であれば後述する顆粒球が上がってきます。
・顆粒球(GR:Granulocyte)
細菌などの異物を捕食することで戦う白血球の仲間です。細菌感染がおこると白血球のなかでもこれが増えることが多いです。
・リンパ球(LY: Lymphocyte)
白血球の中でウイルスと戦っているときに増える細胞です。T細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞などアニメ「はたらく細胞」でもおなじみの仲間たちです。
・単球(MO: Monocyte)
細菌やウイルスを捕食して体を守ります。筆者の経験として顆粒球が増えるときに先に単球が増えてから顆粒球が増えるという性質をもっております。
・ヘモグロビン(Hb: Hemoglobin)
血液中の酸素を運搬するたんぱく質。酸素の輸送船です。血液が赤いのはヘモグロビンによるもので、貧血は主にヘモグロビンで判定いたします。ヘモグロビンが足りないと、酸素を全身に運ぶことができず、頭痛や動悸、ふらつきの原因となります。
・ヘマトクリット(HCT: Hematocrit)
血液全体に対する赤血球の容積の割合(%)。血が濃いか薄いか。低いと貧血、高いと多血ということですが、脱水でも高くなるので評価には注意が必要です。昔はヘマトクリットで貧血、多血を判断したようですが今はだんだんとHbで判断することが多くなっている印象です。
・平均赤血球容積(MCV: Mean Corpuscular Volume)
赤血球1個当たりの大きさの平均を表します。低いと小球性貧血と呼ばれ、原因としては鉄が足りていないことが多いです。血液疾患的にはほかにもサラセミア、鉄芽球性貧血などが小球性貧血に当たります。大きいと大球性貧血と呼ばれビタミンB12や葉酸が欠乏していたりすることがあります。
・血小板(PLT: Platelet)
ケガして血が出た時に血小板がお互いにくっつきかさぶたを作って止血します。かさぶたの素です。少ないと出血しやすくなりあざができやすくなります。多いと血が固まりやすくなり、心臓や脳の血管が詰まる心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まることとなります。
・CRP(C-reactive protein)
体内で炎症や組織が壊れると肝臓で合成され血液に放出されるたんぱく質です。感染が起きたり、関節リウマチなどの自己免疫疾患などで熱が出たりすると上がる値です。どこの部分で炎症が起きているかまではわからないのですが、基本的には高ければ高いほど重症度が高くなる印象です。熱や痛みなどの症状と合わせてCRPを見ることで治療効果の判定材料の一つとして大いに参考になるのですが、経験的に症状の推移よりも少し遅れて上がり下がりするので注意が必要です。
・HbA1C
赤血球のタンパク質であるヘモグロビンとくっついたブドウ糖の割合を示す数値(%)です。ヘモグロビンとブドウ糖がくっつくと赤血球の寿命(120日)が尽きるまで離れないのでこの割合は過去1~2か月の血糖値の平均を反映するといわれています。糖尿病の診断や治療効果の指標として使われます。
血液検査装置
富士ドライケムNX 700
糖尿病や肝臓の状態など、その場で迅速に血液検査
血液の成分である血清を使った検査も当院では15分以内に調べることができます。通常の採血(1.5ml)の採血となります。調べられる項目は以下の通りです。
・総蛋白(TP: Total Protein)
血液中に含まれるたんぱく質のことです。総蛋白≒アルブミン(栄養)+グロブリン(免疫)という構成なので、グロブリン(免疫)≒総蛋白-アルブミン(栄養)と言い換えることができます。総蛋白はその方の免疫力(グロブリン量)を推測したいときに評価する検査となっております。
・アルブミン(Alb: Albumin)
アルブミンはその方の栄養状態を表します。肝臓で作られ、血管内の水分が血管の外に漏れだすのを防ぎます。栄養状態が悪かったり、肝臓の機能が落ちていると下がってしまい、むくんだり、胸水、腹水がたまる原因となります。
・GOT(glutamic oxaloacetic transaminase) / GPT(glutamic-pyruvic transaminase)
急性肝炎、慢性肝炎、アルコール性肝炎、脂肪肝など、どちらも肝臓が悪いときに上がる値です。ではどうして二つ測るかというと、急激に進行する肝炎の急性期ではGOT>GPTとなり、回復期にはGOT<GPTとなる特徴があるからです。また、GOTは心筋>肝臓>骨格筋>腎臓の順に多く含まれ、肝疾患以外にも心筋梗塞、心筋炎、溶血でも上昇が認められる臓器特異性の低い酵素なのに対し、GPTは肝臓特異性の高い酵素であり、上昇しているときには肝臓に障害が生じている可能性が高いなどの違いがあります。
国際的にはAST/ALTが使われるのですが、当クリニックの検査データではGOT/GPT表記になるのでこちらで解説いたしました。
・γ-GTP(γ-gamma-glutamyl transferase)
薬が合わなかったり、アルコールの飲みすぎ、脂肪肝で上がる値です。また胆道という肝臓で作った消化液を十二指腸へ流す管に障害がおこる病気(胆石、胆管炎、胆道がんなど)で上がってくることから後述するALPとともに胆道系酵素ともいわれております。
・ALP(Alkaline Phosphatase)
肝疾患、胆石、胆管炎などで上がり、γ-GTPとともに胆道系酵素と言われています。ただ、ALPは肝臓以外にも骨、肺、小腸粘膜、胎盤などで産生されているので、骨の病気、妊娠後期でも上がってきます。また代謝が亢進する甲状腺機能亢進症でも上がる場合があります。どの組織で異常が起きているのか特定するためにALPアイソザイム(ALP1:肝臓、胆道 ALP2:肝臓 APL3:骨 ALP4:胎盤 ALP5:小腸 ALP6:免疫グロブリン結合型)を調べることもできますが、院内の迅速検査では行うことは難しく当院ではSRLへ外注を依頼することとなります。
・総ビリルビン(T-Bil: Total bilirubin)/ 直接ビリルビン(D-Bil: Direct Bilirubin)
総ビリルビン=直接ビリルビン+間接ビリルビンの関係になっています。
直接ビリルビンが高いと肝炎、胆石、胆管炎などの肝胆道系の疾患が疑われます。間接ビリルビンが高いと溶血性貧血などの血液が壊されてしまう病気を疑います。間接ビリルビンは古くなった血液を処理する際に血液の成分であるヘモグロビンが分解される過程で生成される黄色い色素です。これが肝臓でグルクロン酸抱合という処理を受けて水に溶けやすい直接ビリルビンになり、胆汁の成分となります。スクリーニング検査としてはまず総ビリルビンを評価して高値だった場合には追加で直接ビリルビンを評価して、肝胆道系疾患なのか血液疾患なのか鑑別を行ったりします。
・LDH(Lactate Dehydrogenase)
人間のほぼすべての細胞に存在する酵素のため、細胞が壊されるとなんでも上がってくるというものです。例えば筋肉が壊される横紋筋融解症や肝臓の細胞が痛む肝炎、心臓への血流が足りなくなることで心臓の筋肉が壊れてしまう心筋梗塞などでもLDHが上がってきます。また悪性リンパ腫などの悪性腫瘍も自分の細胞を壊しながら増殖していくのでLDHが上がります。このような性質があることからLDHの値をしっかり読んで病気を正しく解釈できるかはある程度の経験を要する検査となります。
・アミラーゼ(AMY: Amylase)
高いと膵炎もしくは耳下腺炎が疑われます。アミラーゼはデンプンやグリコーゲンを分解する酵素で唾液腺と膵臓で分泌されます。上昇したアミラーゼが唾液腺由来なのか膵臓由来なのかは膵臓型アミラーゼであるP型アミラーゼ(AMY-P)という項目を提出すればわかるのですが、こちらは院内迅速検査ではできず委託業者(SRL)にお願いすることになるのでお時間をいただくことになります。
・尿酸(UA: Uric Acid)
尿酸が高いと痛風になるという話は聞いたことがあると思います。2/3が腎臓から尿として排出され、1/3が腸管から排出され便として排出されます。腎臓が悪いと尿からの尿酸の排出が落ちるので高くなる傾向にあります。DNAの塩基としてアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4種類があることは有名ですが、このうちのAとGはプリン塩基、CとTはピリミジン塩基と言われています。尿酸にはよくプリン体というお話が出てくると思いますが、プリン体はプリン塩基(A,G)のことで、プリン体の最終産物が尿酸となります。つまりDNA、RNAなどの核酸のゴミが尿酸ということになるわけです。ATP(アデノシン3リン酸)というアデニン(A)を含んだプリン体は生きていくエネルギーに必要な物質であり実は7-8割のプリン体はこれをつくるために内因性に産生されております。食事で得られるプリン体は体全体の2-3割ということになります。
核酸は強い「うまみの素」でレバー(牛、豚、魚関係なく)、白子、カツオなどに多く含まれ、尿酸が高いお酒の代表であるビールと相性が抜群なのでとても厄介です。このような食生活を続けていると食餌性に得られるプリン体は全体の2-3割といっても高尿酸血症に注意が必要になってきます。
・血中尿素窒素(BUN: Blood Urea Nitrogen)
高いと腎機能低下、脱水、消化管出血(後述するCrがあまり上がっていないのにBUNが高い場合)などが疑われます。体内でたんぱく質が分解されると生じる有毒成分アンモニアを肝臓のオルニチン回路で無毒化した最終産物が尿素窒素で、腎臓で排出される血中に溶けているゴミみたいなものです。腎臓の機能が弱っているとこれを排出することができず、上がってきます。また脱水だと相対的に血中に溶けているゴミの濃度が濃くなるのでBUNは上がってきます。消化管出血でBUNが上がる理由は消化管内に流れた血液中のタンパク質が分解されてより多くのアンモニアを産生することで結果的にゴミである尿素窒素が増えてしまうことが原因とされています。このとき後述する腎機能を示すCrの値はBUNほど上昇しないのでBUN/Crの比は上昇することになります。
・クレアチニン(Cr: Creatinine)
クレアチニンが高いと腎機能の低下が疑われます。クレアチニンは筋肉のクレアチニンの代謝産物ですので筋肉量が多い方は数値が大きくなる傾向があるようです。BUNと同じく腎臓で処理すべき老廃物(ゴミ)ですがBUNは脱水や消化管出血で上がり、Crは筋肉量が多いと上がるという異なる性質をもっているので、BUNとCr両方評価して腎機能、脱水、消化管出血などを評価することになります。
・クレアチニンキナーゼ(CK: Creatine Kinase)
高いと全身の筋肉、心臓の筋肉に障害が起きていることが疑われます。CKは骨格筋、平滑筋(腸などの筋肉)、心臓の筋肉、脳に分布しています。筋肉の挫傷や横紋筋融解症、甲状腺機能低下などで起こるミオパチー(筋肉の病気の総称)、心筋梗塞で上がってきます。高脂血症の薬の副作用として横紋筋融解症があげられるので、内服している方は定期的にこの値を評価して上がっていないかを確認されている方も多いかと思います。
・クレアチニンキナーゼMB型(CK-MB: Creatine Kinase MB)
CK-MBが上がっていると心臓の筋肉に障害が起きていることが疑われます。前述のCKは全身の筋肉の障害でも心臓の筋肉の障害でも上がってきますが、CKにはMM型(骨格筋型)、MB型(心筋型)、BB型(脳型)の3タイプがありそのうちの心筋型を指します。胸が締め付けられるような胸痛がある方で心筋梗塞を疑う方にはCKだけでなくCK-MBも採血項目に入れることで全身の筋肉のうちの心臓の筋肉に障害が出ているかも評価できるので、心電図のデータと合わせて、循環器専門病院へ緊急搬送を相談する際に説明することができます。欠点は心筋梗塞の発症から4-6時間経たないと上昇していないことがあり、上がっていないからと言って心臓に障害がないとは言えない(測定が早すぎた)ことでしょうか。
・ナトリウム、クロール(Na: Sodium、Cl: chlorine)
体液中に溶けている塩の量です。大部分は食塩(NaCl)として摂取され、摂取された量と同じ量のNaが尿に排出されてバランスを調節しています。高いと脱水、低いと嘔吐や下痢などで塩分が喪失している状態や水の飲みすぎなどが考えられますが、世にはNa欠乏性脱水というものもあり、これを解説すると本が一冊出来上がってしまうので割愛させていただきます。バランスが大事で高すぎても低すぎてもダメで、状況に応じて適度な水分と塩分を補給するのが大事になってきます。
・カリウム(K: Potassium)
カリウムは腎臓の機能が落ちると高くなります。また腎臓の機能が悪い方が野菜や果物を生食するとカリウムの排出機能が落ちているので高くなります。一方で嘔吐、下痢でカリウムは喪失するのでそういった方はカリウムが下がります。Kは98%が細胞内に存在し、前述のNaは細胞外に90%存在しその濃度勾配が体の電気的活動を規定しているため、カリウムは高くても低くても心臓のリズムに影響し不整脈の原因となります。極端な低カリウム、高カリウム血症は心停止に至ることがあるためカリウムの調節は慎重に行う必要があります。
・カルシウム(Ca: Calcium)
甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能亢進症や骨が解ける病気(悪性腫瘍骨転移、多発性骨髄腫)などで高くなります。一方でプラリアなど骨粗しょう症の薬を投与した後ではカルシウムが低くなることがあるので注意が必要です。カルシウムは活性化ビタミンDの力で腸管から吸収されるのですが、慢性腎不全の方はビタミンDを腎臓で活性化する力が弱っておりカルシウムが下がる傾向にあります。カルシウムの99%はリン酸カルシウムとして骨に存在し、約1%が細胞内や血中に存在します。血中ではアルブミンというたんぱく質と結合しているため、血清アルブミンが4g/dl以下の場合はPayne補正式(補正Ca濃度(mg/dl)=実測Ca濃度+4-アルブミン濃度(mg/dl))を使って補正して正しいカルシウム濃度を算出しなくてはいけません。正常値は8.8-10.1㎎/dlですが12㎎/dlを超える高カルシウム血症ではせん妄、昏迷、昏睡といった意識障害が起こる可能性があるので注意が必要です。血清カルシウム濃度が7㎎/dl未満の重度の低カルシウム血症は全身の筋肉痛、けいれんなどのテタニー症状を起こすのでビスフォスフォネート製剤という骨粗しょう症の薬を使用されている方は特に注意が必要となります。
・無機リン(P: Inorganic Phosphorus)
リンはカルシウムとともに骨の主な構成成分です。骨や歯の形成、エネルギー代謝に必要なミネラルです。食事が極端に取れていないいわゆる飢餓状態ではひどい低リン血症が認められることがあります。この時にリンをはじめとしたミネラルの補充をせず栄養だけ急激に補充するとリフィーディング症候群という意識障害やけいれんなどの症状がおこることがあるので特に災害現場では注意が必要とされております。一方で、慢性腎不全の方ではリンの排出ができなくなり高リン血症が認められる傾向にありこの状態が長く続くと血管や軟部組織へリン酸カルシウムが沈着して石灰化がおこり、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まるとされています。
・総コレステロール(T-Chol: Total Cholesterol)
血液中のすべてのコレステロールの合計量を示します。
当クリニックではT-Chol, TG, HDLを迅速診断することができますが、LDLを迅速診断することができないのでLDLはFriedewaldの式(T-Chol=HDL+LDL+1/5TG)で算出します。ただしTG≧400mg/dlの場合もしくは食事をしてきてしまった場合にはLDLをこの式で算出することができません。そのときにはnon-HDL-C(=T-Chol-HDL)をLDLの代わりに用いて170㎎/dl以上を高non-HDL-C血症、150-169㎎/dlを境界型高non-HDL-C血症とすることにしております(動脈硬化疾患予防ガイドライン2022年版に準拠)。non HDL-Cは空腹時以外でも測定でき、高いほど動脈硬化(脂が血管壁にくっつき血管が硬くなり、血液の通り道が狭くなる)、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高いことがわかっており治療の指標となります。
・中性脂肪(TG: Triglyceride)
中性脂肪の値は食事の影響が大きくすぐに変動してしまうため、採血前夜より12時間以上絶食、禁酒にした状態で採血する必要があります。基準より高い場合は脂肪肝、肥満などが考えられ、急性膵炎や動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高くなります。一方でネフローゼ症候群、甲状腺機能低下症などの病気でも中性脂肪が上がるのでそういった病気が隠れていないか調べることも大切です。
・HDL-コレステロール(HDL-C: High Density Lipoprotein-Cholesterol)
末梢(脳血管や心臓の血管)の余分なコレステロールを肝臓へ逆輸送して血管壁へ脂が蓄積して動脈硬化になっていくのを防ぐコレステロールで「善玉コレステロール」と呼ばれています。これに対してLDL-C(Low Density Lipoprotein-Cholesterol)はHDL-Cとは逆に肝臓から抹消血管へコレステロールを運び動脈硬化を起こしてしまうので「悪玉コレステロール」と言われています。
悪玉コレステロール(LDL-C)を減らし、善玉コレステロール(HDL-C)を増やすのが理想ですが、それにはジョギング、ウオーキングなどの有酸素運動を行うことや青魚などの不飽和脂肪酸を多くとることが望ましいとされます。
当クリニックでは療養計画書を患者様と一緒に作成しどのようにして動脈硬化を防ぎ脳梗塞や心筋梗塞を起こさないような生活をしていくか考えていく治療を行っております。
いきなり治療薬を開始するということではなく、まずは生活習慣の改善でできるところまでやりどうしても難しいところはお薬でサポートするというやり方で一緒に考えていきたいと思っておりますのでいつでもお気軽にご相談ください。
土曜日、日曜日も相談、採血、処方を受け付けております。
感染症検査装置
富士ドライケムIMMUNO AG2
新型コロナウイルス抗原検査やインフルエンザ抗原検査を15分で行う検査装置です。富士フィルムの写真現像の銀増幅技術による感度・特異度向上技術を採用しており、ウイルス、細菌などの抗原検出感度が向上。抗原量が少ない発症早期の検体でも検出が可能となりました。また装置による自動判定で人による目視判定より客観的に判定できるようになっています。この装置により検査できる抗原項目は以下の通りです。
・SARSコロナウイルス抗原キット / インフルエンザウイルスキット(AB判定可)
一回の鼻咽頭ぬぐい液で新型コロナウイルス抗原、インフルエンザA抗原、インフルエンザB抗原の3種類を判定できるキットです。
・A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット
咽頭ぬぐい液で溶連菌の評価を行うことができます。
・マイコプラズマ抗原キット
咽頭ぬぐい液で評価可能です。従来マイコプラズマ抗原キットは感度が低いことが問題でしたが、銀増幅技術によりイムノクロマト法を高感度化し発症早期の少ない抗原量での検出精度を向上。高感度でありながら特異度の高さも維持しています。
・RSウイルス抗原キット/アデノウイルスキット
鼻腔ぬぐい液、鼻級吸引液、咽頭ぬぐい液のどれでも評価できます。
・アデノウイルス抗原キット(眼)
結膜滲出液を含む涙液、角結膜ぬぐい液を採取することではやり目(流行性角結膜炎)の原因ウイルスであるアデノウイルスを検出することができます。
網羅的迅速遺伝子検査装置
BioFire® SpotFire®
(2025年9月頃導入予定)
新型コロナ、インフルエンザも15分で判定
15種類の起炎病原体のPCRを同時に行い企業秘密の製法で15分で結果が出る装置です。
一度の鼻腔検査で15種類の病原体の有無が評価できてしまいます。
15種類の起炎病原体の項目は以下の通りです。
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)
季節性コロナウイルス
インフルエンザA
インフルエンザA/H1-2009
インフルエンザA/H3
インフルエンザB
RSウイルス
アデノウイルス
ヒトメタニューモウイルス
ヒトライノウイルス/エンテロウイルス
パラインフルエンザウイルス
百日咳菌(Bordetella pertussis)
パラ百日咳菌(Bordetella parapertussis)
クラミジア・ニューモニエ(Chlamydia pneumoniae)
マイコプラズマ・ニューモニエ(Mycoplasma pneumoniae)
抗原検査では評価することができなかった、百日咳やパラインフルエンザウイルスも評価することができ、しかもPCR検査なので感度、特異度ともに抗原検査よりも優れております。一度コロナの抗原検査を行ってしまうとこの検査を行うことはできません。
費用は3割負担の場合、5000円程度となります。
アレルギー
スクリーニング検査
DropScreen A-1
たった1滴の採血でアレルギーがわかる
指先採血で20μlの少量の採血でたった一滴の指先採血(20μl)で41項目のアレルギー検査が30分で可能です。大人はもちろん、採血が難しい小さなお子様でも検査を行うことができます。検査当日に結果をお渡しすることができます。
費用は3割負担の場合、5000円程度となります。